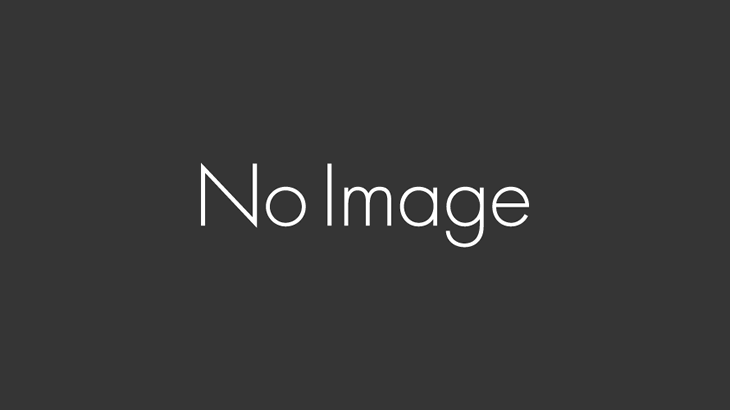内容が「分かりやすい本」と「分かりにくい本」。
どちらの本が良い本でしょうか。
多くの人は、
「そりゃ分かりやすい方が良いに決まってるよ」
と言われるかもしれません。
中には
「良いとはどういう観点でか分からないので答えられない」
と言われるするどい?めんどくさい?人もいるかもしれません。
とはいえ、社会の中では
分かりやすいものがすごく求められています。
そして逆に、分かりにくいものはすぐ批判にさらされます。
教育における分かりやすさ
では、教育という点においての分かりやすさとは何を意味するのでしょうか。
学ぶうえで「分かりやすい」と感じるのは、
・1つは、自分で理解可能な範囲内である可能性。
・もう1つは、何も引っかかるところがなくスッと入ってきている。
ということを意味します。
1つ目は自分の新たな学びがないのは明白で、ここに大きな成長があるとは思えない。
もう1つは一見良さそうですが、他者の思考回路を辿っただけであるため印象に残りにくい。
そのうえ、分かった感じはあるので復習の必要性が生まれにくい。というデメリットがある。
そういう意味で、分かりやすさは「自分で考えて学ぶ機会を奪ってしまう」とも言えるわけです。
今の傷つかせない安心安全な社会にはぴったりなのですが、反面、それで良いのだろうかとも思うわけです。
大人になるということ
大人になることの1つの指標として、
「すっきりしないもの」を自分の中に含み置けるか、ということがあると思います。
もやもやすることや相反する感情:アンビバレントなどなどを心に置くことことは、
その期間で心の器のストレッチしているようなものだと思います。
学ぶ過程でも、「こういうことかな?」「どうなんだろう?」とはっきり分からない概念を頭の中に含み置くことで、頭の成長はもちろん、こころの器を広げる機会になると考えると、
「分かりやすい学び」は大人になる機会を奪ってしまうことにもなるんじゃないかと思っています。
「分かりにくさ」への価値を改めて考えたいなと思う今日この頃です。