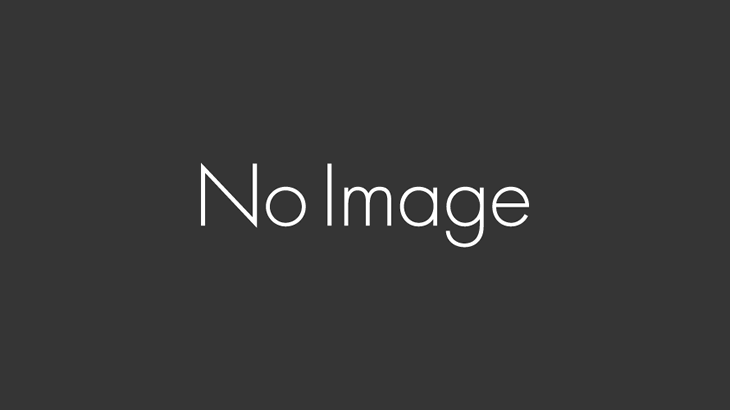前回「分かりやすい」が一概に良いものではないという話を書きました。
何事にも表と裏があるように、良い(ように見える)面も悪い(ように見える)面も両面あるものです。
特に“見せ方”が発達した今だからこそ良いようにも悪いようにも見せることができるのですが、
「楽」の価値観も世の中を覆っているので、それと相まって「分かりにくい」は虐げられているように見えます。
「楽」からの要請
話を学びに戻していきます。
前回は「分かりやすい学び」がいろんな機会を奪っている可能性について触れました。
この「分かりやすい学び」は「楽」と結びついてますます加速していっています。
学んでもらいやすくするために「教材は学習者が受け取りやすいもの」であるべき、という話はまぁ100歩譲って分かるとして、「学習者が学びたくないもの・興味関心がないものを学ばせても意味がないので、学習者の学びたいものだけを教材として扱うべき」なんてことを言う人たちもいます。
成長とは
成長とは、その人が変わるということ。
変わるということは、それまでの形とは変わるということなので、
多少なりとも苦しみや混乱、窮屈さなどを経ていくものである。
それは「成長痛」や「筋肉痛」、格闘技における「型」などでも明らかだと思います。
もちろん、本人が熱中するなどでその過程を気づかない間にクリアしている場合もあります。
しかし、その熱中できる分野とそれによる学びがうまくかみ合うことはなかなか難しい。
(やり切れるだけの余裕が本人にもその周りにも必要)
となると、「学習者が学びたいもの」だけで学びを進めるのであれば、ただただ成長の機会が奪われていくことにはならないだろうか。
また、集団教育のような場であると、その「学びたいもの」が統一されることがとても難しいように思える。その結果、探究の授業のように一見「学習者が学びたい領域を」「自主性に任せて」いるように見えて、形だけや周りに合わせてその場をやり過ごす(ことが一番「楽」)ケースも多々あるように思える。
「よく聞こえるもの」はその良さが高ければ高いほど実現が難しいことでもあるので、もしそれが簡単に実現しているようであれば、外側や見栄えだけになっている可能性は高い。
「楽」と「不快でない」の相乗効果
この「分かりにくいものは嫌」→「分かりやすくあるべき」という流れと同じように、
「この表現はエロいグロいなどの刺激が強いから嫌な気分になる人がいる」→「もっとマイルドな表現にするべき」
みたいなことも世の中にあふれています。
つい最近も、20歳前後の人からのコメントで、
「はだしのゲンの表現が気持ち悪くてしんどくなったから、表現マイルドにするべきだ」という意見がありました。
同じような話として、社会全体でも昔話がどんどんマイルドな話になっているということが聞かれます。有名どころでは日本昔ばなしの「猿蟹合戦」や「かちかち山」とか、書籍では『本当は怖いグリム童話』なども有名でしたね。
生そのものの刺激(血や死、エログロ、個人の悪意や性根、集団の怖さなど、果ては人智を越えた存在)を避けて、
極力マイルドにしてあげて、刺激は無思想の刺激(多色光や効果音などのエフェクトによる刺激)ばかりにしてしまうことは、人の成長にどういう影響を与えるだろうか。
巷にあふれる「99.9%除菌」みたいなものも、「ややこしいものは嫌」「便利」「安心安全」みたいな部分を上手く突いてヒットを維持していると思われる。でもそういう流れで、この「菌との共生」みたいな部分を悪として排除することは、人の生命維持にも欠かせない営みでもある菌を否定することになります。
これが人間に何をもたらすだろうか。
無機質に形作られたな安心安全なものばかりに囲まれてしまったときに、人間と人間の有機的な関わりに耐えられるのだろうか。
人間なんていろんな狂気を抱えているようなものなので、普段からこのややこしい有機的な刺激に慣れることで人付き合いが成り立つようなものだと思っています。その感覚的な慣れがないままに人間の狂気にさらされると人付き合いはますます難しくなるでしょう。
「感覚がマヒしてようやく人間としての正常値」なんじゃないかなと思いつつ、最近のアレルギーや感覚過敏、不登校の激増なんかが頭をチラついてならないです。
今の時代だからこそ「分かりにくさ」への価値を改めて考えたいなと思う今日この頃です。